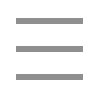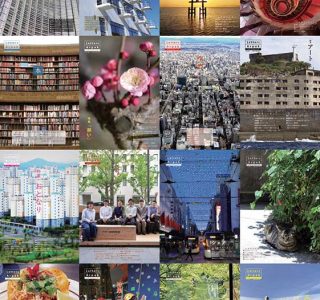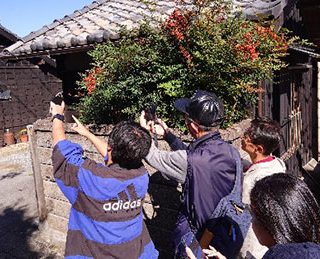レターズアルパック
Letters arpak適塾路地奥サロン報告
第66回適塾路地奥サロンでは、広島大学大学院教授の田中貴宏氏をお招きし、「デジタル技術を活用して『都市の理解』を広げる―まちづくり支援を目的として―」というテーマでご講演いただきました。
「デジタル技術を活用して『都市の理解』を広げる」
講師 広島大学大学院 教授 田中貴宏氏
(第66回 2024年12月6日)
第66回適塾路地奥サロンでは、広島大学大学院教授の田中貴宏氏をお招きし、「デジタル技術を活用して『都市の理解』を広げる―まちづくり支援を目的として―」というテーマでご講演いただきました。
講演では、まちづくりにおける複雑な課題に対し、デジタル技術がどのように活用できるかについて防災や環境、賑わい創出など様々な事例を通じてお話いただきました。特に印象的だったのは、食べログの評価データを使った都市特性の分析です。「札仙広福」の都心部において飲食店評価データをプロットし、人気の飲食店が集まるエリアの特徴を明らかにするという試みでした。質疑応答では、「食べログの評価データの妥当性」について議論がありました。SNS分析は有効なインサイトを得られる一方で、バイアスやサンプルの偏りが存在するため、多角的なアプローチが必要だと感じました。
今回の講演を通じて、デジタル技術は都市の特性をより深く理解し、効果的なまちづくりを支援できる可能性があると実感しました。講演で得た知見を活かし、今後のまちづくりにデジタル技術を効果的に取り入れ、持続可能で魅力的な都市づくりを目指していきたいと思います。(城本大輝)
「名古屋駅裏から駅西へ―東海道新幹線とリニア新幹線をめぐる開発主義」
講師 名古屋市立大学 准教授 林浩一郎氏
(第67回 2025年2月21日)
第67回適塾路地奥サロンは、名古屋市立大学大学院人間文化研究科准教授である林浩一郎氏をお招きしました。今回の適塾路地奥サロンは初めて名古屋での開催となり、「名古屋ならではのお話が聞きたい」と事務局で論文を検索し、リニア新幹線の開通に伴う名古屋のまちづくりの研究をされている林先生に話題提供をお願いしました。
林先生は、特に名古屋駅西エリアをフィールドに、都市の変化と住民の暮らしを生の声や写真資料から緻密に分析し、社会学の視点から社会の潮流に位置付け、これまでとこれからの駅西のまちづくりを分析・構想しようと試みる研究をされています。名古屋駅西は俗に言う駅裏と呼ばれる場所で、そのルーツは戦後の闇市に遡ります。東海道新幹線の開通により闇市は消え去りましたが、十数年前までは夜の店が立ち並び夜通しネオンの灯りが煌々と街を照らしているような場所でした。その風景が一変するきっかけになったのがリニア新幹線の開発工事です。まちからネオンが消え、まさにその場所にリニア新幹線の駅舎が建とうとしています。そのまちの変化に伴い、そこで暮らす人々の生活も劇的に変わろうとしている様子は実に興味深く、駅西エリアには今までほとんど縁がなかったのですが、まちづくりに関わるコンサルタントとして、名古屋駅西は目の離せない場所になっていると思いました。
会場には、論文共著者の木田先生、植田先生、駅西のまちづくり協議会のメンバーをはじめ名古屋駅周辺のまちづくりに関わってきた方々、再開発に関わるゼネコンの社員、名古屋の若手設計者や学生等が集まり、様々な視点から忌憚のない熱い議論が繰り広げられました。また名古屋で開催してほしい!との声もたくさんいただき、良い時間になったと思います。(石橋昂大)
適塾路地奥サロン実行委員会 城本大輝・石橋昂大
250号(2025年3月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索