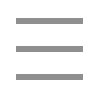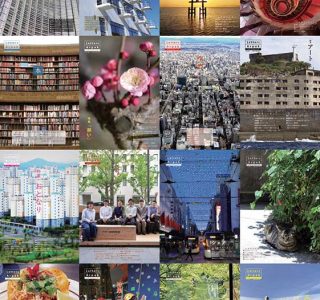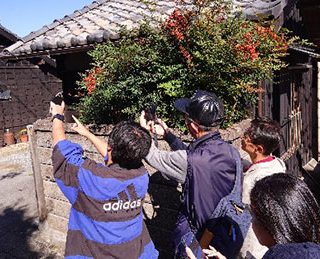レターズアルパック
Letters arpak脱炭素と脱炭素'経営'の違いへの理解を全国に広める
前号の江藤の記事で、豊田市やトヨタ紡織Sunshine、兵庫県・神戸市での脱炭素経営に関するスクールをご紹介しましたが、社会背景としてはサプライチェーン全体での排出量開示義務化の動きが着実に進みつつあります。
前号の江藤の記事で、豊田市やトヨタ紡織Sunshine、兵庫県・神戸市での脱炭素経営に関するスクールをご紹介しましたが、社会背景としてはサプライチェーン全体での排出量開示義務化の動きが着実に進みつつあります。
国際的には、既にISSB(国際サステナビリティ基準審議会)のScope3の開示義務化(2023.6)、EUがリードする「Pathfinder Framework」[WBCSD(持続可能な開発のための世界経済人会議)のガイダンス]などがあり、日本においても、同基準をベースに民間のサステナビリティ基準委員会(SSBJ)が日本版の基準策定(2025.3予定)、2026年3月期の有価証券報告書から3月期企業の同基準に基づく開示が始まる予定です。さらに、削減貢献量(Avoided Emissions)についても、GHGプロトコルでの算定手法の検討も開始されています。
この間、宗像市や古賀市をはじめとした糟屋地域の自治体が共同で開催したセミナー(ほか九州経済産業局、省エネルギーセンター様など)や、⿓⾕⼤学サステナビリティ推進室主催の講座(ほか環境省、京都市環境部長様など)において基調講演と参加者を交えたフロアディスカッションのコーディネーターをさせていただいています。
これらでは、(1)単なる「脱炭素」ではなく、「脱炭素経営」を考える、(2)自らの力で脱炭素経営計画を組み立てるプロセスを大切にする、(3)地域の企業がコミュニティとして結び付き共に支え合う、ことを常々お伝えしています。特に、地域経済循環の面から重要な地域に根差した中小企業の皆さんの〝関わり〟の大切さについては、皆さんに特に響いているようです。
冒頭のスクールでは、Scope3の自主算定もスタートしています。地域のSustainability確保に向け、気候変動対策・脱炭素(環境)、地域の多様なステークホルダー間の関わり(社会)、地域経済循環(経済)のトリプルボトムラインの統合的解決に向け、引き続き貢献していきたいと考えています。
サスティナビリティマネジメントグループ 畑中直樹
250号(2025年3月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索