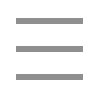レターズアルパック
Letters arpakロジックモデルを活用した文化芸術事業の評価マネジメント
各分野の計画策定において頭を悩ますのが「評価」の項目。かつてはPDCAサイクルで評価していたものの、近年はEBPMが浸透し、KPI/KGIといった数値目標を設定することが当たり前になりつつあります。
各分野の計画策定において頭を悩ますのが「評価」の項目。かつてはPDCAサイクルで評価していたものの、近年はEBPMが浸透し、KPI/KGIといった数値目標を設定することが当たり前になりつつあります。
一方、設定した数値目標をどのように評価するのか、そもそも数値目標を達成すれば計画を実現したことになるのかについては、あまり議論されることがなく、その結果、計画の担当者は「評価疲れ」に陥ることもしばしばあります。
私が主に関わる文化政策分野では、計画や事業の評価を数値で図ることがそもそも難しいとされていますが、近年は「ロジックモデル」を導入することも増えてきました。私自身も日本評価学会が養成する評価士を受講・認定を受け、「八尾市芸術文化推進基本計画」に掲載されたリーディングプロジェクトの評価マネジメントや、「第8回横浜トリエンナーレ」の事業評価の取組に関わっています。

八尾市でのロジックモデルワークショップの様子
ロジックモデルは、施策や事業が目的を達成するまでの論理的な因果関係を体系的に図示するものですが、関係者が集まり、「この事業は最終的にいつまでに何を達成したいのか(社会的インパクトや最終アウトカム)」、「その目的は誰に対するものなのか」、「取り組んでいる事業は本当に目的達成につながっているのか」といったことを議論しながら、仮説をつくりあげていくプロセスが重要だと再認識しました。また、作成したロジックモデルをもとに、アンケート調査やヒアリング調査を行い、仮説が達成されているかを検証する中で、数値目標が達成されていない場合はロジックモデルが間違っていたのか、アクションを変えたほうが良いのか等、意見交換していくことが評価マネジメントにおいて大切です。調査・計画策定だけでなく、その後の事業伴走を評価の側面からも応援していきます。
地域産業イノベーショングループ 江藤慎介
249号(2025年1月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索