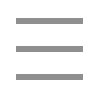レターズアルパック
Letters arpak海洋プラスチック問題の解決にむけた実証実験
海の中のプラスチックごみが増え続けています。それによって海洋の生態系や、観光・漁業などの人間活動にも影響が及んでおり、全国で、世界全体で、この問題に取り組むことが求められています。
海の中のプラスチックごみが増え続けています。
それによって海洋の生態系や、観光・漁業などの人間活動にも影響が及んでおり、全国で、世界全体で、この問題に取り組むことが求められています。
大阪湾を漂うごみの9割はペットボトルや容器等の生活系プラスチックだと言われており、大阪にとって海洋プラスチック対策は大きな課題となっています。こうした中、この年末から年始にかけて、大阪府及び大阪湾プラごみ対策ネットワークの支援のもと、インバウンドを含めた観光客が多く訪れ、春からの万博会場にも近い大阪南港のATC(アジア太平洋トレードセンター)の協力を得て、瀬戸内海のプラスチックごみ対策、とりわけカフェやコンビニで提供されるテイクアウト飲料カップの適切な回収等に協力していただくことを目指した実証事業に取り組んでいます。
この実証事業では、大きく(1)テイクアウト飲料カップの回収実験、(2)多言語でのリサイクルボックスへの異物混入防止の啓発、(3)ATCの従業員やオフィスワーカーへのプラスチック回収の啓発、を実施します。まずは(1)からの開始で、本事業のメインターゲットである観光客の多い3か所を選んでテイクアウトカップの回収ボックスを設置しました。
(1)のテイクアウト飲料カップの回収実験は、特典なしと特典ありの2つのパターンで実施し、効果の違いを検証します。最初は特典なしでひっそりとスタートしたのですが、しばらく観察していると、回収ボックス横に設置した案内板を眺める観光客がちらほらと見られ、海洋プラスチックへの関心の広がりを感じました。
その一方、回収ボックスのごみの調査では飲料容器の不適切排出やリサイクルに適さない飲み残しなどが幾つも確認され、こうした啓発や行動変容の必要性が改めて浮き彫りになりました。
今後も実証事業の広がりに併せて回収ボックス調査の継続実施やアンケート調査等を行い、海洋プラスチックへの関心の広がりや、実際の行動変容の効果等を把握し、最終的には海洋プラスチック対策の解決に繋がる取組へと進めていく予定です。
サスティナビリティマネジメントグループ 長沢弘樹
249号(2025年1月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索