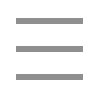レターズアルパック
Letters arpak特集「脈」
文脈、山脈、脈絡、脈拍など「脈」は(意味のある)つながりを表す言葉です。建築や都市計画ではコンテクスチュアリズムという言葉を連想する方もおられるでしょうか。地域の歴史や文化などのコンテクスト(=文脈)を尊重して建築や都市を作っていくという、現代ではある意味で当たり前の考え方です。そこでは地域の見えないコンテクストをいかに見い出すかが問われます。
文脈、山脈、脈絡、脈拍など「脈」は(意味のある)つながりを表す言葉です。建築や都市計画ではコンテクスチュアリズムという言葉を連想する方もおられるでしょうか。地域の歴史や文化などのコンテクスト(=文脈)を尊重して建築や都市を作っていくという、現代ではある意味で当たり前の考え方です。そこでは地域の見えないコンテクストをいかに見い出すかが問われます。
一方、かつて磯崎新は建築を連歌のように関連づけて都市を作っていくというコンセプトを提唱していたことがあります。こちらはいかに魅力的なコンテクストを作り出すかが問われます。
コンテクストを見い出すのも作り出すのも建築家やプランナーに求められる能力。観察力と想像力を磨きましょう。2025年最初のレターズアルパックをお楽しみください。
「なりたい自分」とは/地域再生デザイングループ 浅田麻記子
大阪・関西万博の公式キャラクター・ミャクミャクは「なりたい自分を探して、いろんな形に姿を変えている」そうですが、2024年は年齢的にも節目の年であり、「なりたい自分」を考えることが多かったように思います。今の状況は大学生の頃までに思い描いていた「なりたかった自分」とは全く異なっていますが、まだその頃の「なりたかった自分」を諦めるわけにはいきません。少しでも近づけるように、仕事はほどほどに…を今年の目標としたいと思っています。とはいえ、現在、私史上最も頑張っている伊丹空港近くでの公園も万博期間中に一部開園するため、まだまだ山場の続く年明けとなりそうです。
脈々と受け継がれてきた大阪の博覧会の歴史/都市・地域プランニンググループ 石川聡史
大阪の博覧会というと、1970年の日本万国博覧会EXPO’70が有名です。1990年の国際花と緑の博覧会を覚えている方も多いでしょう。しかし、1983年に大阪城公園で大阪城博覧会が開催されたことを知らない人も多いのではないでしょうか。ミャクミャクのようなキャラクターはいなかったと思いますが、それにあわせて大阪城公園駅と大阪城ホールがオープンし、御堂筋パレードが行われるなど大阪のまちが盛り上がっていたことを覚えています。
このように博覧会の歴史が脈々と受け継がれきた大阪で、今年は何かと話題の大阪・関西万博が行われます。どんな盛り上がり方を見せてくれるのか期待したいと思います。
都市・大阪 その脈々/ソーシャル・イノベーティブデザイングループ 石川俊博
「脈」という話題とのことで、そういえば当社は本社が京都で京都には古都の歴史・文化が「脈々」と受け継がれ…のような話を考えたのですが、書いていて大して面白くなかったので私が住む大阪について書くことにします。
大阪は、京都と異なり都市のイメージが安定しない印象があります。京都よりも早く都がおかれた歴史を持ちながらも古都のイメージはなく、国際港湾都市、宗教都市、商業都市、工業都市などなど、さまざまな姿に変化を遂げてきました。
一つのイメージにとどまらず、変転や転生を無限に繰り返すその姿こそが、大阪においては脈々と受け継がれてきた都市の精神なのかもしれないと感じます。
葉脈の如きかな/サスティナビリティマネジメントグループ 植松陽子
ここ数年、小グループで無理せずをモットーに低登山を楽しんでいます。四季折々の自然を感じながら、身も心もデトックスすることができる良い時間です。春は芽吹き、夏は木漏れ日、秋は紅葉、冬は落ち葉を踏みしめ、葉っぱだけでも様々な楽しみ方ができます。
葉っぱの葉脈は複雑縦横に絡み合い、水と栄養を送る「血管」と、太陽光を存分に浴びるために葉を横に向ける「骨」の役割を果たしています。一部寸断されても他のネットワークを選択でき、リスク回避も万全ですね。
私も葉脈の如く、よどみなく循環し続け、誰かの何かの支えとなるべく、しなやかな一年にしていきたいと思います。
ミャクからはじまる思考旅行/地域再生デザイングループ 木下博貴
「脈」と聞いて困り果て、万博のミャクミャクを調べることにしました。ミャクミャクは、細胞と水がひとつになったことで生まれた、ふしぎな生き物だそうですが、ここで興味を引いたのは細胞です。2024年はSTAP細胞の騒動から10年となり、様々なメディアが不正に関する課題を論じています。一方で、数年かけて研究過程を見直し、なぜ誤りに至ったのか原因究明されていることも知りました。単なる不正で終わることなく、再生医療の実現に向けた飽くなき研究を知り、まちづくりに携わる自分も感化されるところとなりました。まさか、脈から細胞、まちづくりにつながるとは思いませんでしたが、有意義な思考旅行となりました。
地方で感じる人とのつながり/都市・地域プランニンググループ 城本大暉
私は学生時代、研究活動や学生団体の活動を通じて地域に深く関わる中で、多くの人々との出会いから貴重な経験を得ました。地域住民や行政担当者、地元企業の方々との意見交換を通じて、自分の視野を広げ、地域の課題や可能性を多角的に捉える力を養うことができました。それぞれ異なる立場や背景を持つ人々との対話は、単なる知識の共有にとどまらず、共感や信頼を築く大切さを実感させてくれました。このように培った人脈や経験は、現在も自分の活動の基盤となり、新たな挑戦を後押ししてくれる大きな財産です。これからも業務を通じて、新たな出会いを大切にしていきたいと考えています。
脈々とつなげる?/生活デザイングループ 竹内和巳
某キャラクターを想起するタイトルになってしまいましたが、最近いくつか、標題について考える機会がありました。
・野球界の選手会加入・不加入
・自治会不参加世帯の自治体へのゴミ収集要望(税の使い方含めて)
・某パック社の使われない互助会費
カテゴリはてんでバラバラですが、社会基盤が安定してきた中で、共助の役割の再咀嚼が求められているのは同じで、社会の縮図を感じます。もっとも、咀嚼前に、団結が必須となる社会情勢が訪れる可能性もありますが…少し真面目な文章になってしまいました。引き続き、社会への違和感を抱えつつ、都市や住まいのあり方を楽しく考えたいと思います。みなさま、本年もよろしくお願いいたします。
脈拍とテンポを楽しむ話/生活デザイングループ 堂本健史
まず脈拍を測る。私の場合、だいたい1分間に60拍だ。このテンポをスマホのメトロノーム・アプリで再生し、イヤホンで聴く。再生音は耳触りにならないものを選ぶ。この状態で一日を過ごす。
歩くときは自然と手足の動きはだいたいテンポに合ってくる。このテンポが歩きやすいと感じる。
仕事のときは集中するうちに音が消えていく。ふと我にかえり音が戻る。その音を楽しんでみたり、気分転換に珈琲を飲んでみたり。
なにか焦りがあるときには、思い直して脈を測ってみるとよい。脈とメトロノームは同じテンポだろうか。
不整脈人生/都市再生・マネジメントグループ 中井翔太
不整脈と診断され、早30数年経ちますが、今のところ循環器系の大病などはなく、現在に至ります。
国立循環器病研究センターによると「不整脈とは、脈がゆっくり打つ、速く打つ、または不規則に打つ状態を指す。」とのことですが、振り返ると私のまだ短い半生も、一定のリズムではなかったなと感じます。同じ歩調で進めるとそれは安定した人生と言えるのでしょうが、私の場合、これからも立ち止まったり、全力で走ったりを繰り返しながら、平均すると健康的な脈拍値にある。そのような少し人より短い人生を歩むのだろうという小さな覚悟を、当寄稿を通じ、得させていただきました。
目指せ離島の山脈!/企画政策推進室 中村孝子
大学時代は、京都の某大学のバックパッキングクラブ(日本の大学で最初にできたバックパッカーのクラブ)に所属して、登山が中心の旅をしていました。必死に登った山の頂から連続する山脈の風景は、格別で心身ともに浄化されて清々しい気分になります。以前の特集でも書きましたが、日々、「SHIMADAS 」(シマダス:日本の島ガイド)と「しま山100選」(日本離島センター)をチェックしています。
コロナも終息したので、体力のあるうちにあこがれのスイスアルプス、マチュピチュなど、海外の絶景ルートを攻めてみたい気もしますが、まずは仲間と一緒に日本の島山からチャレンジしようと思っています。
脈打つ仕事とのめぐり逢い/都市再生・マネジメントグループ 西村創
「脈」という言葉から、私はまず「血液の流れ=鼓動」を連想します。仕事において「脈を感じる」という瞬間を考えると、新たな命が生まれるような瞬間、新しい人との出会いや、意見を交わし合い、時に熱く議論する中で、想定を超えた化学反応が生まれる瞬間に近いものがあるのではないでしょうか。
「これってもしかして?」と心が動くような小さなきっかけを大切にし、そこから生まれる可能性を丁寧に育てていくことで、やがて大きな「脈」へとつながるのだと思います。
今年も、皆さんと共に「脈打つ」ような一年を歩んでいければ、とても幸せです。
脈絡のない話/ソーシャル・イノベーティブデザイングループ 橋本晋輔
我が家の子どもはよく「今の話と関係ない話やけどな…」と突然脈絡のない話を始めます。聞いている側としては話題が急に変わるので少し困ることもありますが、よく考えると、こうして自由に話せるのは「安心して言える場」があるからこそだと思うのです。
このことは、私たちが関わるまちづくりや職場の環境づくりにも通じます。安心して意見を言える場があれば、活発な議論が生まれるきっかけになります。脈絡のない話から素晴らしいアイデアが出てくることもあります。「関係ない話やけどな」と言える空気感をいかにつくるかを、これからも大切にしていきたいと思っています。
脈拍があがる=ドキドキまちづくり(名古屋圏)/都市・地域プランニンググループ 福井秀樹
愛・地球博、JRセントラルタワーズ開業、名古屋城本丸御殿復元、MRJ初試験飛行(後に失速)などはドキドキしました。今後はリニア開通や名鉄名古屋駅の再開発にドキドキするでしょう。昨年では愛知県スタートアップ支援拠点施設「ステーションAi」。トヨタ自動車はじめ多くのものづくり企業が集積する産業県・愛知県ですが、世界で生き残って行くためにはスタートアップと協業して付加価値を高めてゆく必要があるということです。製造業に限らず、ステーションAi発スタートアップの新事業・サービスが、全国・全世界のドキドキまちづくりを創造していくことを期待しています。
意味のない脈の計測がもたらすもの/建築プランニング・デザイングループ 増見康平
脈という言葉には、妙に親近感を感じる。幼少期から心肺機能強化のトレーニングで、脈を測り、自分の運動強度や心肺機能としての回復力を数値化していたのだが、サッカーから遠のいた現在でも、性懲りもなくスマートウォッチで脈を測っている。特に分析しているわけでもないので全く意味はない。このように意味のない継続(データ収集)が世の中にはごまんとあり、現時点では意味を見出せないものが多分にある。これらに対して多様な切り口で、価値を見出す結果に結びつけられる(つまり、これまでの脈をつむぐことのできる)、そんな固定概念に捕らわれない、幅のある人間でありたい。
各務原アルプスの向こう側へ/建築プランニング・デザイングループ 間瀬高歩
令和6年度は、3箇年担当してきました岐阜県各務原市における小中学校の建替基本方針策定業務の最終年です。市教育委員会が設置されている産業文化センターの高層階からは、各務原台地の北端に連なる各務原アルプスと称される標高350mほどの山並みの稜線や遠景には美濃・郡上の奥深い緑の山脈を眺望することができます。各務原アルプスの稜線は、岐阜市、関市との境界で初心者から中級者まで楽しめる複数の登山コースがあり、濃尾平野の広大な景色を楽しむことができます。
昨夏以来、山歩きから遠ざかっているため、学校施設建替業務を納める今春には、各務原アルプスを歩き、向こう側からの眺望を楽しみたいと思います。
未来を共に創っていく/地域産業イノベーショングループ 山口泰生
いよいよ、大阪・関西万博が来年開催されます。仕事柄、「万博」というキーワードは頻繁に登場し、現在関わりのある自治体でも、プレ万博イベントが地域で開催されるなど、徐々に機運が高まっているように感じます。その公式キャラクター「ミャクミャク」の名には、未来への脈々と続く想いが込められているようです。「脈」という言葉は、単なる繋がりだけでなく、生命力や発展、そして歴史の重みすら感じます。
関西万博は、そんな「脈」を未来へと繋ぐ、イノベーションが生まれ、文化が交流し、新たな価値観が創造されるのではないでしょうか。私自身も、この「脈」の中にしっかりと身を置き、未来を共に創っていきたいと思います。
なんの脈絡のないつまらない話/都市再生・マネジメントグループ 山本昌彰
「脈」から「採血」の話。こんな体質の人いませんか?採血で気分が悪くなる人。実は私がそのひとりで、いつもベッドで採血(そこで笑わんといてください(笑))。
全く恥ずかしい話ですが、これは子供のころからで、健康診断がやってくるといつも憂鬱でした。最初は、気の持ちようだとも思っていましたが、どうやら「血管迷走神経反射」と呼ばれるもの。いわば体質のようなものらしいのです。最近になって、大抵の病院では採血用ベッドの用意をしてくれるようになり、安心、安心。
なんでこんな話をしているかな。「脈」の話というので。「なんの脈絡のないつまらない話」ですみませんでした。では次の人のお話を読みましょう。
誰かの気持ちに寄り添うこと/ソーシャル・イノベーティブデザイングループ 依藤光代
脈という漢字の成り立ちは、血や気など体の中を流れるもの、だそうで、「気」の巡りが含まれるのが東洋らしいと思います。
例えば大事な人や居場所を失った時などは、気が落ち込み、流れが滞りがちです。相談を受ける側はつい相手を励ましたくなるのですが、しかし落ち込むのは自然な反応です。
安心して落ち込める、ありのままの自分の感情や意志を誰かに受け止めてもらえるということが、気の回復や安定につながります。相手に寄り添うということなのですが、言葉以上の深みがあます。
子育てや、職場での関係においても大事なこと。言うほど簡単にはいかないのですが、めざしていきたいところです。
遠い未来の水脈へ/総務部 若林秀和
一昨年末、父が世を旅立ち、様々な引き継などで忙しい日々を過ごしました。早いもので1年が過ぎ昨年末に法要を営み、恥ずかしくない程度のことはやってあげられたと思っています。懐かしむのはこれからです。
法要の席ですが、久々に会う高齢の親戚たちは相変わらずにぎやかにしてくれました。その少し前に私の姉の子(姪)に娘が誕生し、私はおばあちゃんの弟となりました。親戚が集まる中で、姉が赤ちゃんの写真を見せてまわると、「あなたの子どもの頃にそっくり!」と話題にしてくれました。大叔父としては、その姿にただ清らかな水脈のように流れ続けてくれればと感じるところです。
脈を打つ/建築プランニング・デザイングループ 和田裕介
脈と言えば、ランナーは、「心拍数」をイメージすると思います。
「心拍を上げられる」ことは、「全身に酸素を運搬できる能力が高い」ということでが、「最大心拍数-220-年齢」という残酷な公式があるように、加齢とともに、心拍数も上げにくくなってしまいます。
ランニングウォッチで正確に心拍数をモニタリングしていると、公式の正しさや厳しい現実を見せつけられてしまうのですが、今年は年男かつ、やっとの大阪マラソン挑戦の年なので、バタバタと自然の摂理に抗いながら、何かと脈打つ1年を過ごしたいと思います。
脈々と受け継いだ「お正月料理」/公共マネジメントグループ 渡邊美穂
新年号で掲げた抱負の未達成が続き、今年は幸先のよいスタートを切りたいです。テーマ「脈」の意味を踏まえ、自分が脈々と受け継いだモノ・コトで思い浮かんだのは「お雑煮」「おせちのお煮しめ」です。これらのお料理がお正月に並ばないのは寂しさもありますが、何より美味しいので受け継ぎました。そして、受け継いだからには自ずと次世代へと渡す役割があります。今のところ先行きは不透明です。ただ、美味しいという記憶はその可能性を高めるはずです。手間暇かかりますが「美味しかった」の一言を貰って1年をスタートしたいです。本年もどうぞよろしくお願いします。
レターズアルパック編集委員会
249号(2025年1月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索