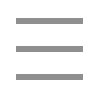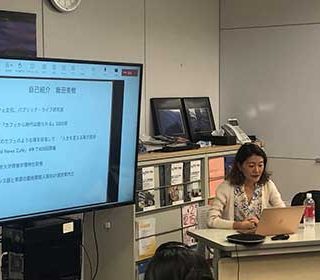レターズアルパック
Letters arpak新参者の初めての手紙
私は、生涯、手紙たるものをまともに書いた記憶がない。ただ、3~4歳のクリスマスイブに、手紙という名の「要望書」を枕元に置いて寝た記憶はある。
私は、生涯、手紙たるものをまともに書いた記憶がない。ただ、3~4歳のクリスマスイブに、手紙という名の「要望書」を枕元に置いて寝た記憶はある。
私の家は、手伝い、大会での優勝や成績表の◎の数など、なにかしらの頑張りがあって初めて、欲しいものが手に入るハウスルールがあった。そのため、何の頑張りもなくプレゼントを提供してくれるなんとも素晴らしいおじさん、そう、サンタさんに当時の私は心を躍らせた。
特異なことに、私は「要望書」に、サンタさんからの返事をもらうスペースとして罫線を書いた。私はどんな返事をサンタさんに期待したのか。プレゼントの選定理由が知りたかったのか、サンタさんの存在を確かめたかったのか、記憶にはない。ただ、私の欲しいものが記載された「要望書」に対して、サンタさんに返事を求める、しかも、こどもが起きないかヒヤヒヤしている状況で、だ。どうやら、当時から厄介なこどもであったようだ。
幸いなことに、私の家を担当するサンタさんは、日本語に精通しており、「要望書」にドンピシャでは応えられなかった謝意とともに、プレゼントの説明や来年の約束を交わしてくれる余裕のあるサンタさんであった。
当時を思い返すと、私はプレゼントより手紙の方がうれしかったように思える。クリスマスに枕元を見た時の良き記憶は、プレゼントでなく、サンタさんからの返事であった。「要望書」の頁を開いていたはずのノートが閉じていることに気づき、ノートを手に取って、一心不乱に頁を捲る、そんなわくわく感を久しく思い出した。そう思うと、私の「要望書」は、サンタさんからの返事を伴うことによって初めて、「手紙」としての役割を担っていたのかもしれない。
近年、電話、メール、SNSなど、情報伝達ツールの多様化が目覚ましい中、手紙が他の追随を許さないのは、このわくわく感ではなかろうか。差出人のみが分かった段階で、手紙の封を切って開く、そのプロセスと間は、タイパを求める時代に逆行した風情ある手紙の良さである(もちろん、差出人次第だが)。
さて、約30年の時を経て、このレターズの企画に関わることになった私は、どう自分の役割を全うしよう。とりあえず、「手紙」ならではの良さを体現できるアプローチを企画すると意思表明だけしておく。
建築プランニング・デザイングループ、レターズアルパック編集委員 増見康平
247号(2024年9月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索