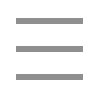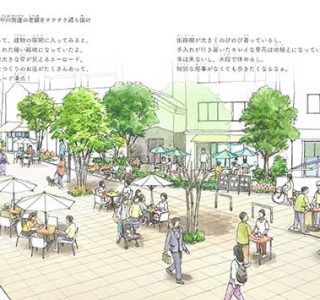レターズアルパック
Letters arpak特集「昇」
新年あけましておめでとうございます。2024年最初のレターズアルパックは年頭らしく「昇」というテーマでスタッフからの小文を集めました。「昇」はもともとは太陽がのぼるという意味だそうです。『枕草子』のあまりに有名な書き出しは「春はあけぼの…」。
新年あけましておめでとうございます。
2024年最初のレターズアルパックは年頭らしく「昇」というテーマでスタッフからの小文を集めました。
「昇」はもともとは太陽がのぼるという意味だそうです。『枕草子』のあまりに有名な書き出しは「春はあけぼの…」。太陽がまさにのぼり始める直前の、山ぎわがほのぼのと明るくなっていくさまの美しさにあらためて着目したのです。敬服すべき清少納言の美的センスです。
私たちも経済性や合理性ばかりに踊らされることなく、社会を美的にデザインしていくことに貢献していきたいものです。
日が昇る、日の出湯/地域産業イノベーショングループ 有田建哉
京都に引っ越してきてから「銭湯巡り」にハマっています。旭日昇天の勢いで仕事に励む日々からのリフレッシュを求めて駆け込んだ銭湯に魂をふやかされてしまったのが、銭湯にハマったキッカケでした。調べてみると、京都は平安時代末期に初めて湯屋(湯浴み)が開かれた、銭湯の聖地だそうです。京都には80ヶ所以上の銭湯がありますが、今までに巡った湯は8箇所(少なっ!)。中でもお気に入りは、京都駅南に徒歩10分、日が昇る、日の出湯です。銭湯に入ると2時間は出ません。一週間溜め込んだ疲労をゆっくり湯に溶かし昇華させています。そして、昇天しそうな自我を取り戻すため、じっくり時間をかけて自分と向き合い、気持ちと思考を整えます。これで次の月曜日にはスッキリにっこりです。興味があれば一度、銭湯で魂をふにゃふにゃしにてみませんか?お供させていただきます。
昇と降/都市・地域プランニンググループ 石川聡史
「昇」は上昇を意味するので、反対語は下降の「降」でしょうか。
これまでの風潮では、成長や大きくなることが良しとされ、「昇」はポジティブな感じですが、「降」は暗いイメージを想像してしまいがちです。
ですが、これから社会全体が縮小していく時代を考えると、これまでのような上昇・拡大志向だけでは社会も人の気持ちも持たないような気がします。昇ろうが降りようが、そこに良し悪しはなくただ違うステージに進んでいくだけ。そう考えるとそこで得られる新しい経験や気づきに、価値を見いだしていくことが大事なのではないかと思います。
キラキラキャンペーン/生活デザイングループ 内野絢香
最近、業務でパイロットに取材をしたせいか「昇」と聞くと、そのパイロットを連想してしまいました。
同世代だったパイロットの口から出てくる言葉には、今後の自分への希望や期待が感じられ、やっぱり何かに向かってまっすぐ前を向いている人は、上昇気流を巻き起こし、キラキラしているなと思いました。そんな思いに触発されたのか、取材の日から私の中で「キラキラキャンペーン」を実施中です。まずは、住んでいる団地の共用ベランダで育てだした、枯れそうなハーブたちのお世話をしつつ、目標である私なりの「住み開き」の形をベランダで模索する日々をはじめてみました!
人を見る/総務部 宇都宮和文
以前の職場では昇任するためには年に1回の昇任試験で良い点数を取ることが必須だった。もちろん普段の勤務評定が一番のウェイトを占めるのだが、仕事の良し悪しを評価するのは難しい。
試験とは目に見える形で優劣をつける手っ取り早い方法だったのだろう。人が人を評価する人事評価制度では普段からその人を良く見ておかなくてはならないと考えるが、私は普段から相手を見て仕事ができているだろうか?この記事を書きながら反省している。
普段から相手をよく見て、眉間にしわよせてないか?顔色悪くないかなど目配り・気配り・声がけができる人になれるよう心がけます。
ウェルビーイングな毎日へ/地域産業イノベーショングループ 江藤慎介
福井県若狭町に新しく出来たキャンプ場「山座熊川」で、「ウェルネスツーリズム」のプログラム開発に関わっています。トレイルウォーキングや坐禅などで自分自身と向き合い、健康的で美味しい食事に満たされるプログラム。あわせてスマートウォッチで「心の疲れ」を測定しているのですが、これが面白いのです。日々の生活の中で「心の疲れ」は増減を繰り返すのですが、何をしているときに心の疲れが上昇しているかが分かり、プログラムで学んだ「リセット」を試すと下降します(多分)。
今年も心の疲れをほどよくマネジメントし、ウェルビーイングな毎日を送りたいと思います。
インクルーシブなまちづくりを夢見て/生活デザイングループ 嶋崎雅嘉
「昇」という字は、ただ単に上に行くという意味だけではなく、「天」や「空」に向かっていく意味が含まれているそうです。何か大きな目標に向かって、一歩一歩着実に進んでいくイメージを思い浮かべます。
私が思い描く「目標」としては、まちで住み、働き、過ごす人たちが、「こんなまちにしたい」「こんなことができたらいいな」と思い描き、それを気軽にチャレンジしたり参加ができる。そんな「場」と「きっかけ」「仲間」があるまちを育てること。それはきっと誰もが楽しく安心して暮らせるインクルーシブなまちになると夢見ております。
自分自身も「広」げたり、「遊」んだり、「出会」ったりしながら、少しでも「昇」っていきたいと思います。今年も皆様お付き合いいただければ幸いです。
『昇運守』に期待を込めて…/都市・地域プランニンググループ 清水紀行
10月末にグループ研修旅行で青森を訪れ、八戸の蕪島神社に立ち寄りました。
日没後に到着したため暗闇の中でチラ見しただけでしたが、その後の居酒屋で「蕪島のご利益はすごいよ。常連さんは宝くじが当たり仕事も大成功」という話を伺い“再び行かねば!”と翌朝にきちんとご挨拶?してきました。
ちなみに蕪島はウミネコ繁殖地として国天然記念物に指定されており、繁殖期には3万羽の大群が訪れるそうです。またウミネコは神の使いで、彼らの糞が当たると幸運が訪れるとか…残念ながら糞には当たりませんでしたが、宝くじが当たった暁にはグループの皆さんを海外研修にお連れしたいと思います。
昇華/建築プランニング・デザイングループ 新開夏織
“昇華”とは、理科で「固体が液体を経ず気体となること」と習いましたが、心理学ではストレスや衝動などへの対処(防衛機制)の一つで、「怒りや劣等感など、社会的には認められないであろう欲求や衝動を学問や芸術活動など社会的に望ましいとされる方向に変化させること」の意味で用いられています。自分のエネルギーを別の(良い)形で表現しようとすることは、大変有益なことだと思います。この昇華を活用するには、(1)自分の感情等を知り、(2)現実に直面し、(3)自己表現することが大事だそうです。
色んなことのある日々の中で、自分とどう向き合い、対処していくかを考えることは、とても重要なことだと感じています。今年は行き詰った時にも“昇華”を意識して、健康に、前を向いて歩いていきたいと思います。
龍/建築プランニング・デザイングループ 杉本健太朗
昇と言えば、龍を連想します。私は昔から龍が好きです。小学生の時は、図画工作展に展示する龍の物語の絵を授業後も居残りしながら、のめり込んで描いていた思い出があります。大人になってからも、お寺を訪れた際は、天井画に龍が描いてあると、思わず見入ってしまいます。また、台湾を旅行した時に、ガイドさんが言っていましたが、5本爪の龍が描かれるのは、皇帝のみしか許されなかったようです。さて、私が好きな虫の世界にも龍がいます。トンボです。英語でDragonfly(ヨーロッパではドラゴンは邪悪な存在として描かれがちですが)、かっこいいですね(なお、イトトンボは、Damselfly)。
プロ野球では、2023年は、猛虎の年でした。2024年は、昇竜に期待です。燃えよ、ドラゴンズ!
おのぼりさん おくだりさん/サスティナビリティマネジメントグループ 張玉鈴
京都の西北にそびえる愛宕山は古来より多くの人の信仰を集めている。愛宕山では、愛宕詣りを終えた下山者がこれから山頂の愛宕神社に向かう登山者に「おのぼりやす」と、逆に登りの人は下りてくる人に向けて「おくだりやす」と声を掛け合うのだという。この独特な挨拶の習わしは、愛宕山のほかにもう一か所、愛媛県の西日本最高峰・石鎚山に残っている。石鎚の山頂にも神社があり、行き交う人々は「おのぼりさん」「おくだりさん」と挨拶をするそうだ。
思うにのぼりとくだりは一揃いで、この生も産み落とされ昇天するまでの1セットとみることができる。何かが昇るとき同時に降りていくものがあり、下(くだ)るときも同様に登るものがあることに心を寄せていたい。
ぎふのまち/地域再生デザイングループ 辻寛太
最近は、地元の岐阜市を紹介する機会が増えてきました。岐阜市は平坦なため、高い場所からは市街地を一望することができます。私が紹介する際は、まちの全体を見てもらいたいので、高いところに登って案内しています。岐阜市の全体が見れる高い場所は二か所ありますが、その一つが市街地の北にある金華山です。山頂の岐阜城からは、岐阜のまちと長良川を一望することができ、天気が良ければ名古屋のビル群まで見渡すことができます。
岐阜市に訪れた際はぜひ金華山に登り、信長が見た同じ景色を体感してみてください。
次のステップ/総務部 仲野めぐみ
「昇」という漢字は1つ上のステップへあがるというイメージがあります。我が子達は現在中学3年生と小学校6年生で、4月からそれぞれ高校、中学へと次のステップを踏み出そうとしているところです。最終学年という事もあり、1つ1つ行事が終わっていく寂しさを感じつつも、この1年間はコロナで規制だらけの3年間を乗り越えた日常のありがたさを噛みしめながら、どの行事もそれぞれに立派な姿を見せてくれました。たくさんの感動を子ども達からもらいました。
新しい環境になっても、大きく羽ばたいてほしいと切に願っています。
階段のとりこ/企画政策推進室 中村孝子
建築めぐりをしていると階段の美しさにハッとすることがあります。職人技が光る重厚な彫り物の親柱や手すり、フィボナッチ整列が潜んでいる螺旋階段などなど。時にはエントランス空間を支配するその存在感に圧倒されます。階段は上り下りする目的で作られたものですが、観方によると芸術作品でもあります。
近年は、「階段の魔術師」ともいわれる巨匠村野藤吾の軽やかな曲線に目覚めて、階段目的に旅に出ることもしばしば。素敵な階段に出会うと、天にも昇る気分になります。今年もいい出会いがありますように。
昇り調子にあやかりながら/都市再生・マネジメントグループ 西村創
年を重ねるごとに右肩上がり、昇り調子とはいかない年齢になりつつあります。下の子どもが1年生からはじめた小学校のサッカークラブのコーチをはじめて1年以上が経ちました。子どもとの共通の趣味ができるとともに、やっとパパコーチ友もできて、少しだけ子育てに参加している気になっております。まあ連れ合いからは、自分が好きなサッカーしてるだけやと言われていますが・・・
そんな中でも、ものを教えるという行為の難しさを実感しております。すぐ調子にのる子、ほめて伸ばさないといけない子、何をいってもマイペースな子。2年生ぐらいだとなかなかに動物園の園長ぐらいの気持ちですが、元気な子どもたちの昇り調子にあやかりながら、今年も公私ともに一年頑張りたいと思います。
目線を上げて視野を広く/都市再生・マネジメントグループ 羽田拓也
40代に突入してからというもの、上昇しなくていいものが順調に上昇し、上昇させたくても上げづらいものが出てくるなど、体の変化がはっきりしてきました。自分自身を俯瞰しながら順応しつつありましたが、昨年、自分では上げようのないもの、不可能なものも加わりました。
こうした状況では焦燥感、雑念みたいな“気持ちの摩擦”を起こしがちですが、そういう場面も俯瞰しながらなんとか前向きなマインドや熱意に昇華させ、摩擦によるロスを減らし、所属チームや関わる各地域の熱量アップ、ひいては、より良い地域づくりへの貢献に少しでもつなげていく1年にしたいと思っています。
2024年/ソーシャル・イノベーティブデザイングループ 深谷弓希子
レターズ新年号が発行されるのは、2024年ですが、この原稿を書いているのは2023年。
年末年始は何をして過ごそうか、大掃除の計画や食べたいものなど、思いをめぐらせています。読みたい本や見たい映画もあるので、それも楽しみにしています。
2024年の良いスタートをきれるように、年末年始を有意義に過ごしたいと思います。
皆さまにとって、2024年が、上昇していくような、より良い1年になりますことをお祈りしています。
スカイスパイ(ゲイラカイト)/都市・地域プランニンググループ 福井秀樹
お正月に「昇」と言えば、私が子どもの頃はやり始めた大きな目玉の描かれたゲイラカイトを郊外の大樹林地の片隅にあった採石場であげたことを思い出します。カイトが青空に吸い込まれるようにどんどん昇って行き、やがて目玉が見えなくなるほどに。実は今、その場所に関する調査に関わっています。砕石場と思っていたところは、違法開発により中断された開発地で、今はグラウンドになっているものの、周りの樹林地は今も未整備公園のままです。半世紀も経って思い出の場所の調査に関わるとは・・・。私が住む名古屋市内には「昇」に限らず、感覚と結びついた思い出の場所ばかりで、そんな場所のまちづくりに関われることをうれしく感じながら業務に取り組んでいます。
日々これ精進/ソーシャル・イノベーティブデザイングループ藤田始史
昔自分の名前を姓名判断したことがあります。結果は「波乱富貴」。昇沈がありながらも、最終的には幸せになるとのことでした。喜んでいいのかどうか分かりません。それが本当かどうか気になって、占いが出来る友達に占ってもらいました。「フジタの人生の絶頂期は70代です。老後はお金に困りません。それまでは波が多々あります。」とのことでした。遅すぎますよね、絶頂期。
70代までだいぶ先なのか、あっという間なのか分かりませんが、どうやらそれまでは下積み生活が続くようです。少しでも早く昇っていけるように、今年も精進を続けます。よろしくお願いいたします。
新しい形を探して/建築プランニング・デザイングループ 山崎博央
ここ数年、卸売市場の再整備に係わる機会が多く、北は東北から南は四国まで、あちこちの市場へ移動の毎日です。その市場再整備の仕事でよく出てくる言葉が「物価上昇」や「家賃上昇」。何か気分が下がりますね。市場で働く方々と話をしていても、なかなか明るい話題になりにくいですが、地域の食を支える大事な社会インフラである卸売市場です。いろんな産地から集まったさまざまな野菜や果実、魚や花などが売場いっぱいに並ぶ光景は見ていてワクワクするものがあります。このワクワクがそれぞれの地域に広がるような新しい市場の形をみつけられないだろうか、などと考えつつ、気持ちを上げながら日々精進していきたいと思います。
はじめての「社会生活」/地域産業イノベーショングループ 山部健介
2歳半の娘が今年から幼稚園に入る予定です。つい先日まで赤ん坊だったのが、今では人一倍元気に公園を走り回って(冬でもたまに裸足で)、休日は一緒にサッカーをするようになり、日々成長を感じているところです。
はじめての集団行動、社会生活をできるのか…不安ではありますが、「パパちゃん、あたち幼稚園いくの!」と思いのほか楽しそうに、「プレ幼稚園」に通っているのを見ると、上手くアジャストしてくれそうな気がしています。娘が成長していく姿をみると、私自身も公私ともに成長していかなければ…と思
う次第です。
生と死 その瞬間の美しさ/地域再生デザイングループ 山本貴子
千葉県の犬吠埼という岬では、私の産まれた日・産まれた時間に、高地や離島を除き日本で一番早く日が昇ります。それを知って、ある年の誕生日に、日の出を観るために犬吠埼にでかけました。
日の出なんて、それまでに何度も観ていたけれど、その時に観た日の出は、やっぱり特別です。日が昇るこの瞬間に、私の人生が始まり、ここまで生きてきたということを振り返り、家族・友人、周りにいてくれる人や育ってきた環境に対して、感謝の気持ちでいっぱいでした。そして、日が昇り、沈んでいくのと同じように、私の人生も終わる時が来る。その日まで、ちゃんと生きていきたいと思えた光景でした。
超昇寺城と城/都市再生・マネジメントグループ 山本昌彰
「超昇寺城」という城、ご存じでしょうか。私の家の近く奈良西大寺にその跡があります。室町時代、超昇寺の僧が出自とされる在地土豪の超昇寺氏の築城らしいのですが、城といっても、天守などありません。そもそも、皆さんが描く天守は織田信長が創出したもの。城は、弥生時代の環濠集落からはじまり、武士の館や領主の居館などを含め、全国に4~5万以上あるともいわれ、うち天守をもつものはわずかです(さらに現存天守は12城だけです)。ここ超昇寺跡は、今は竹林で何もありませんが、よくみると空堀などの土塁らしきものも確認できます。室町時代、領主のお城をイマジネーションし “攻城”してみましょう。
今年は「昇」らない/公共マネジメントグループ 渡邊美穂
ここ数年、新年号に寄稿して1年間の抱負を宣言しています。寄稿したら忘れてしまう抱負でもあるのですが、昨年は確か「チル」だったかと。華々しく散るというよりは、相変わらず砕け散ることが多い1年でした。
今年は「昇」。あがるのはよいのですが、その後はさがることもあります。自分は興味関心、感情など、あがって、さがって、せわしない性質で自身に往生しています。ですので、今年は「あがる」ことはしないで「ニュートラル」を意識して行動できればと思います。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
レターズアルパック編集委員会
243号(2024年1月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索