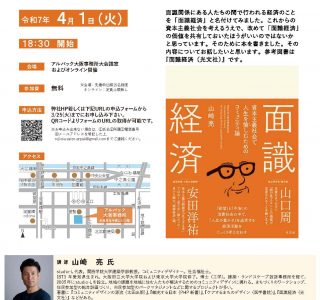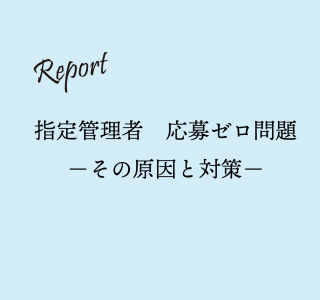レターズアルパック
Letters arpak指定管理者 応募ゼロ問題 -その原因と対策-
指定管理者制度は、住民ニーズの多様化に効率的・効果的に対応し、経費節減を図る目的で2003年に導入されました。この制度により、株式会社やNPO法人など多様な団体が公共施設の管理運営に参入し、民間のノウハウを活用した住民サービスの向上と費用対効果の改善が進められてきました。導入から20余年を経た現在、制度は一定の成果を挙げていますが、一方で近年「応募ゼロ」となる事例が散見されるなど、課題も顕在化しています。本稿では、この「応募ゼロ問題」について事例、原因、対策を整理します。
はじめに
指定管理者制度は、住民ニーズの多様化に効率的・効果的に対応し、経費節減を図る目的で2003年に導入されました。この制度により、株式会社やNPO法人など多様な団体が公共施設の管理運営に参入し、民間のノウハウを活用した住民サービスの向上と費用対効果の改善が進められてきました。導入から20余年を経た現在、制度は一定の成果を挙げていますが、一方で近年「応募ゼロ」となる事例が散見されるなど、課題も顕在化しています。本稿では、この「応募ゼロ問題」について事例、原因、対策を整理します。
1.応募ゼロ問題の事例
「応募ゼロ問題」は、公共サービスの継続の危機に直結します。以下に示す3つの事例では、いずれも長期間指定管理を継続してきた施設が更新時に応募者を得られなかった結果、設置者が異なる対応を迫られました。具体的には、条件を変更して再公募した例、設置者の外郭団体を選定した例、直営に戻した例がありました。これらの対応によって公共サービスの停止は免れたものの、そのリスクが顕在化しました。
2.想定される原因
前項の事例は、いずれも長期にわたり指定管理者が継続していたにもかかわらず、応募者ゼロ問題に直面しました。その原因を3点に整理しました。
(1) 指定管理料の不足
指定管理料の不足が、この問題の最大の原因と考えられます。現在、公共施設の管理・運営に係る費用は様々な理由で増加しています。人件費の高騰や施設の老朽化に伴う修繕の増加は、どの施設にも共通して見られます。
一方、施設固有の要因としては、社会環境の変化に伴う利用実態の変化による業務量の増大も見られます。例えば高齢者施設において、入所者の高齢化が進行することにより、従前よりも日常生活支援のための人員が増大したケースがあります。
こうした費用増大が、指定管理料または指定管理者が受領する利用料金に転嫁されなければ、指定管理者の収支は悪化します。現状、指定管理の約7割は5年です。更新の際には、この間の費用構造の変化を把握する必要があります。
(2) リスク分担の不均衡
指定管理に関連するリスクのうち、重要なものとしては物価変動リスクと修繕リスクが上げられます。物価変動リスクについては、指定管理期間中の物価上昇が指定管理料の算定において予め織込まれておらず、かつ、上昇時の価格改定ルールがない場合、そのリスクを全て指定管理者が負担することを意味します。これは合理性にかける分担です。
指定管理では、一件当たりの修繕費が一定額以下は指定管理者が負担するという条件により、小修繕は指定管理者が負担する分担がよく見られます。この分担の問題は、施設が老朽化するほど、また、設置者が大規模修繕を見合わせるほど、小修繕の発生頻度が増加する点にあります。老朽施設の修繕リスクは大規模修繕の維持決定者である設置者こそ管理できるリスクであるため、これを事業者に転嫁することは合理的でありません。
こうしたリスク分担の不均衡は、指定管理者の費用増加につながるため、指定管理者の経営を脅かします。
(3) 人材確保の難しさ
人手不足が社会問題となるなか、指定管理においても人材確保が応募の障壁となっています。指定期間が3年から5年程度の場合、経営の立場からは期限付きの雇用条件が望ましいものの、労働者側からは不安定な条件と見られます。
また、新規参入の場合、指定管理者の決定から指定期間の開始までの期間に、多くの人員を確保する必要があります。この期間は、新設施設の場合を除くと一般に数ヶ月程度であり、配置人員数が大きい施設ほど、現指定管理者以外の事業者の応募が難しくなります。
これらは指定管理の事業条件・選定手続きを変更しなければ解決できない課題です。
3.応募ゼロ問題への対策
応募ゼロ問題への対策としては、コスト等の上昇や人件費等の高騰といった課題への対応事例の周知を図った国通知「指定管理者制度等の運用の留意事項について(令和6年4月1日総行経第9号行政経営支援室長通知)」が参考となります。
本通知で紹介されている福岡市の事例は、指定管理指定の議決後に締結する基本協定書とは別に、実施協定書を毎年度締結しています。ガイドラインでは、その運用として「指定管理料については、事業者の提案した金額を基に、毎年度、施設所管課と指定管理者が協議を行うこと」としています。
福岡市の事例は、人件費については「労務単価は最新なものを使用」すること、物件費については「備品購入費は施設等の修繕費などリスク軽減に係る費用など、施設の安全確保やサービス水準の維持に必要な経費を適切な積算」することとしています。
指定管理料への具体的な反映の程度が予めわかりませんが、施設運営の実態や社会情勢の変化に対し、かなり広範な見直しをかけることが可能と考えられます。
一方、国通知で紹介された横浜市と札幌市の事例は、公共工事にみられる物価スライド条項と同種の仕組みを、指定管理費のうち人件費の精算に適用しています。スライド条項は、物価変動に対する指定管理料の変更範囲が明確である点で優れます。一方、業務量の変化など物価変動によらない費用増には対応できません。
国通知以外の事例として、福岡市では、指定管理期間が満了を迎える際に、現指定管理者の評価が高い場合は指定期間を通算10年まで延長を可能とする仕組みを設けています。また、予測が立て難く変動要素が大きい修繕費を実績払いに変更することで、修繕リスクの分担の適正化を図っています。
おわりに
応募ゼロ問題は、制度そのものの信頼性と持続性を揺るがす可能性を秘めています。本稿では、その原因として、指定管理料の不足、リスク分担の不均衡、人材確保の難しさの3点を挙げました。また、先進自治体における対策をいくつか紹介しました。これらを組み合わせることで、応募ゼロ問題への対策を講じることができると考えます。
建築プランニング・デザイングループ 堂本健史
251号(2025年9月)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索

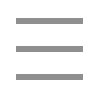

![いずれ木になる、いま気になる話「AI]](https://www.arpak.co.jp/contents/wp-content/uploads/2025/09/251_13-01-320x300.png)