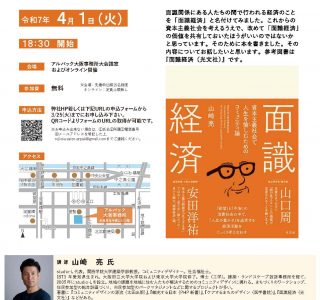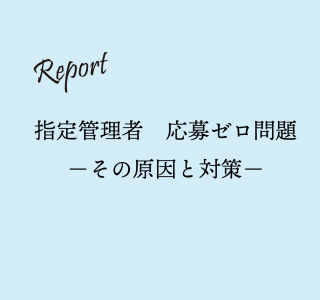レターズアルパック
Letters arpak「にぎわい」の本質を考える
都市計画やまちづくり、施設整備に関する計画の中には、必ずといっていいほど、「にぎわい」という言葉がでてきます。「にぎわい」と聞けば、たくさんの人が集まり活気がある…そんなイメージがありますが、それだけが「にぎわい」なのか?本当に求められている「にぎわい」とは?を改めて考える業務を一昨年度より受託しています。
都市計画やまちづくり、施設整備に関する計画の中には、必ずといっていいほど、「にぎわい」という言葉がでてきます。「にぎわい」と聞けば、たくさんの人が集まり活気がある…そんなイメージがありますが、それだけが「にぎわい」なのか?本当に求められている「にぎわい」とは?を改めて考える業務を一昨年度より受託しています。
東京都北区では、新庁舎建設を契機に、庁舎の低層部において、”にぎわい・交流・協働”が相互に結び付き循環する場(にぎわい施設)の創出を目指しており、アルパックでは、このにぎわい施設の施設方針や事業スキームについて検討しています。
業務では、人流データによる来街者特性分析、オンラインアンケートによるニーズ調査、グループヒアリングやワークショップによる区民意向調査、事業者や地域団体等へのヒアリング調査等を実施し、区民等が求める「にぎわい」に加えて、公民連携の視点から事業者や地域団体等が考える「にぎわい」を探りました。また、学識者や実務経験者等による有識者会議において「にぎわい」について議論していただきました。

ワークショップの様子(1)

ワークショップの様子(2)
さまざまな調査や議論を通じて感じたことは、今回の場合、本当に望まれている「にぎわい」は、その言葉では表現しきれないものだということです。たくさんの人が集まり活気があるということは当然求められているのですが、それ以上に、排除されることなくただそこにいること、誰かとつながっていたりつながっていなかったりすること、自分の小さな可能性を発揮し育てられること…まるで小さな子ども達がいろいろなことを学びながら成長していくような、心がほどけるような温かな場所が求められているように感じました。そして、そうしたそれぞれのシーンが集まることで、結果として、たくさんの人が集まり活気が生まれるのではないかと思います。
「にぎわい」という言葉は、すっと入ってくる便利な言葉だけれども、少し曖昧で、その背景にあるものをしっかりと捉えなければいけないと改めて感じた業務となりました。これまで、私自身も、さまざまな場面で「にぎわい」という言葉を使っていましたが、今後は、より一層、その言葉の意味を探り、「にぎわい」という言葉を使っていきたいと思います。
北区の新庁舎が完成するのは、まだまだ先になりますが、いつか完成した時に、今回の調査や議論を通じて想像した「にぎわい」の姿が実現し、温かな場所となることを願っています。
地域再生デザイングループ 山本貴子
251号(2025年9月)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索

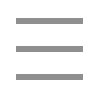

![いずれ木になる、いま気になる話「AI]](https://www.arpak.co.jp/contents/wp-content/uploads/2025/09/251_13-01-320x300.png)