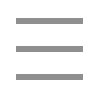レターズアルパック
Letters arpak「ごちゃまぜ」から考える心地よい空間づくり
京都の市街地はコロナ禍を経て活気が戻り、国内外の観光客が行き交う「ごちゃまぜ」な光景が日常となっています。「ごちゃまぜ」という言葉は本来、にぎわいや多様な人々が交じり合うといったポジティブな意味合いがあるはずですが、京都で日常生活を送る私にとっては少し疲れの感情が強い言葉です。
京都の市街地はコロナ禍を経て活気が戻り、国内外の観光客が行き交う「ごちゃまぜ」な光景が日常となっています。「ごちゃまぜ」という言葉は本来、にぎわいや多様な人々が交じり合うといったポジティブな意味合いがあるはずですが、京都で日常生活を送る私にとっては少し疲れの感情が強い言葉です。
一方で、近年の公共空間には「ごちゃまぜ」が心地よく感じられる場も増えているように思います。最近、公共施設や空間の活用等の業務を通じて、さまざまな場所でヒアリングや視察を重ねる中で、「にぎわい」「居心地の良い」「多様な活動が起こる」まちや空間について考える機会が多くありました。
雑感になりますが、それぞれが「ここにいたい」と感じている人が多くいるとき、まちのにぎわいにつながると感じています。その中に、何かを生み出そうとする能動的な人々もいれば、のんびりと寝転んだり、静かに佇むような受動的な人々もいることが理想的です。
そのようなシーンは、「互いに敬意を払い合う秩序やルール」「フレキシブルであり、想定外の利用を許容できる柔軟な空間」、そして、「その場所を好きで居心地よさを保とうとする誰かの存在」があって、はじめて実現できるのではないかと思います。

普段開かれていない場所で知らない人同士が混ざり合う
:湊の芸術祭(坂井市三国)
アルパックで行う社会実験やワークショップは空間を活用する上での諸条件やニーズ等の検証を行うだけでなく、場所と人、その場所に集う人同士の関係性の構築を行うことも重視しています。関係性をつくる中で、互いの領域を尊重しながら「ここにいたい」「あなたもここにいていい」とそれぞれが思えるようになることで、心地よい「ごちゃまぜ」につながるのではないかというのが今の所感です。
今後、人々が尊重され、穏やかな気持ちで集える「ごちゃまぜ」の空間を増やす実践をしていきたいと思っています。京都事務所周辺もそうなればと切に願います。
地域再生デザイングループ 高瀬咲
248号(2024年11月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索