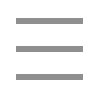レターズアルパック
Letters arpak「不寛容な社会」について
近年、多様性(ダイバーシティ)や社会包摂(インクルージョン)と言った言葉が様々な場面で使われ、自分とは異なる価値観を互いに認めあい、共存・共栄することの重要性がうたわれています。その趣旨に疑う余地はないと誰もが分かっている一方で、世界中で争いは絶えず、生きづらさを感じる人がたくさんいます。
近年、多様性(ダイバーシティ)や社会包摂(インクルージョン)と言った言葉が様々な場面で使われ、自分とは異なる価値観を互いに認めあい、共存・共栄することの重要性がうたわれています。その趣旨に疑う余地はないと誰もが分かっている一方で、世界中で争いは絶えず、生きづらさを感じる人がたくさんいます。
私が、最初「ごちゃまぜ」というお題を聞いた時、『異質なものを受入れない/受け入れることができない「不寛容な社会」』を連想しました。
例えば、ネット社会ではその傾向が顕著です。誰もが手軽に自らの考えを発信でき、時には社会を動かす一助となり得るポジティブな面がある一方、単なる感想やコメント、自分と直接関係ない話題(芸能人の不倫問題等は最たる例)に対しても攻撃的で、論破することを目的としたような書き込みが増え、所謂〝炎上〟状態となりがちです。
このような「不寛容さ」は何故生まれるのでしょう?日本での理由として「島国特有の同質性社会」が挙げられることがありますが、海外にはあてはまりません。理由はひとつではないと思いますが、個人的に腑に落ちたのは、ある精神科医が言っていた「防衛本能の表れ」です。私たちの社会生活はストレスと切っても切れない関係にあります。そのストレスを昇華(消化)させるひとつの手段が異質な者への攻撃(差別と言い換える場合も)を通して、自分の立ち位置を確保し安心感を得る…それが「不寛容な社会」の一側面であるという論です。
しかし、相手のマウントを取って自分の立場を上げる行為は自分の弱さの裏返しです。それでは他者の共感を得られず、結局、社会全体の幸福度が上がることはないでしょう。
心理学用語に「ラディカル・アクセプタンス」という表現があるそうです。良いか悪いかはさておき、現状を受け入れる姿勢のことを意味しています。今の自分自身をありのまま受け入れつつ、リスペクトする自尊心を育むことが、他者を受容する「寛容な社会」に近づくはじめの一歩なのかもしれません。
都市・地域プランニンググループ 清水紀行
248号(2024年11月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索