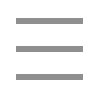レターズアルパック
Letters arpak組織のエントロピー
「ごちゃまぜ」→「乱雑、無秩序」→「エントロピー」と連想し、アルパックの組織について雑感を記す。15年前転職してきたとき、この会社は割と残念な状態であった。1990年代のポストバブル期に規模的なピークを迎えたのち、2000年代は縮小傾向にあったようである。
「ごちゃまぜ」→「乱雑、無秩序」→「エントロピー」と連想し、アルパックの組織について雑感を記す。
15年前転職してきたとき、この会社は割と残念な状態であった。1990年代のポストバブル期に規模的なピークを迎えたのち、2000年代は縮小傾向にあったようである。しかし、2012年に故森脇さんが代表取締役社長に就任され、「ここからV字回復を目指す」と力強く宣言されたことが転機となり、以降は拡大基調となっている(委託外注費を除くネット売上高ベースでみると2010年から2023年で約2倍になっている。いま振り返ると筆者が入社した時期がどん底だった)。
2012年に組織改革を行ない、「専門グループ制」を経営単位としたことが回復の原動力となった。それまでは地域密着型の「地域事務所制」を標榜していたが、アルパックが扱う地域の課題はどんどん高度化していたので、専門家をまとめるほうが時代の流れにマッチしていた。そして、各専門グループには将来のアルパックを担う中堅のチームリーダーを配した。
言い換えると組織を無秩序な状態から秩序のある状態に組み替えたわけだ。エントロピーの増大に抗うのだから最初はエネルギーが必要だったが、ある程度までいくとあとは自己組織化が進んだ。オーガナイズ/組織化は生物のorgan/器官から派生した言葉で、「生命とは負のエントロピーを食べるもの」という説を思い出し、社会的組織と生命体と比べて考えてみるのは面白い。
「秩序」と並んで重要と考えるのが「自由」である。アルパックは後者を重視する人が多い。秩序だけでは息苦しいが、秩序のない自由では人が集まる意味がない。両者のバランス=「秩序ある自由」はなかなかむずかしいテーマだ。
さて、アルパックの組織はこの先どうなっていくのか。地域密着を続け、専門性ももっと磨いていきたい。これらを引き継ぐ第三のあり方はあるのか? 複雑化する社会課題に対し単一の専門性で解くことはむずかしく、異なる専門人材の組み合わせ=「複合化組織」がキーワードと考えている。もうひとつ、閉じた系は平衡状態に向かうので、常に外部から人材を採りいれることが重要である。
総務部 柳井正義
248号(2024年11月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索