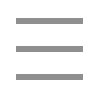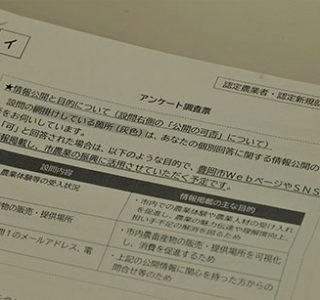レターズアルパック
Letters arpak土と炎の神秘にふれる
かつて京都市内には、清水焼・京焼の登り窯がありました。現在、操業している登り窯は一つも残っていませんが、宇治の山奥にあります。数年前まで、秋が深まると陶芸家の友達が窯焼きのお手伝いをするので毎年見に行くのが恒例となっていました(友達は元同僚の旦那さんです)
かつて京都市内には、清水焼・京焼の登り窯がありました。現在、操業している登り窯は一つも残っていませんが、宇治の山奥にあります。数年前まで、秋が深まると陶芸家の友達が窯焼きのお手伝いをするので毎年見に行くのが恒例となっていました(友達は元同僚の旦那さんです)。深夜に動物が飛び出しそうなハラハラする山道に車で向かいます。下界との気温差は激しく息も白くなります。よくぞこんな山奥に作られたと立派なその姿を見るたびに感動させられます。
火入れは、3日~4日間2交代制で友達の担当は夜からなので、眠い目をこすりながらの参加です。各地から運ばれてきたびっしり積まれた松割木は日を追うごとに減っていきます(松は火力が強いそうです)。緩い斜面にある登り窯の内部は何部屋かに仕切られ、中をのぞくと順序良く器がたくさん並んでいて圧巻です。残念ながら器をいれる窯詰は見たことがありません。窯は正面からみると、芋虫の顔のようでなんだか親近感がわいてきます。とてもかわゆいです。そして窯の中で暴れまくる炎は、まるで龍のようで、熱すぎて短時間しか見ていられません。

窯の横には愛宕さんの「火迺要慎」のお札があります

温度計
一応温度計はありますが、高温になると測れないので、中にある確認用の土器で焼き具合をみながらの真剣勝負です(私はみているだけですが)。窯に木をくべ続けるピーンと張りつめた空間は、神々しくここには火の神さんが宿ると感じざるをえません。陶芸家も同じだと思いますが、土と炎の神秘に魅了されます。コロナ禍でしばらく訪れていないので、そろそろ火入れを見に行こうと思っています。
ちなみに毎日使っている器は、友達の作品です。今日もおいしいご飯をいただきます。
おまけ:窯出しの器が冷めていくときの澄んだ「キン」という貫入音は、器がおしゃべりしているようです。

愛用している器と温度確認用の土器
企画政策推進室 中村孝子
236号(2022年11月号)の他記事
バックナンバーをみる
タグで検索